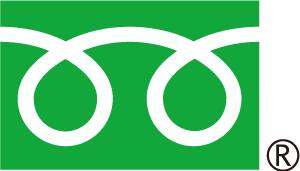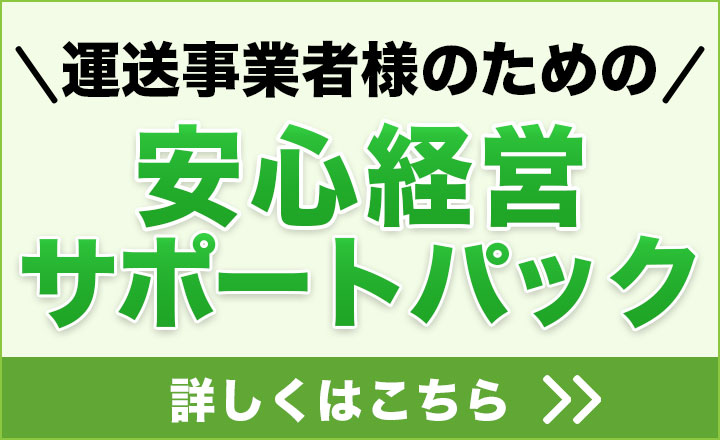今年も残すところ1ヵ月になりましたね。
31日まで、無事故で乗り切りましょう。
1時間目は事業用自動車の特性に合わせた運転
バスやトラックは、小さいサイズのものでも、乗用車などと比較して、その車体はとても大きく重くできています。
プロの運転士は、その大きさと重さから起こる特別な動きを、いつも忘れずに運転しなければなりません。
左側方部は、特に死角の多い場所です。
体をうまく使って、目視で確認しましょう。
✅停止距離は乗用車よりも長くなる
空走距離は、個人の反応レベルの問題ですので、乗用車でもトラック、バスでも変わりませんが、制動距離は車体の重さに大きな影響を受けます。
車種にもよりますが、トラックやバスの制動距離は、乗用車の1.3倍から2倍になることがあります。
✅シンクロ事故の注意
大型車の運転席は、乗用車などよりもかなり高くなっています。
このアイポイントの高さは、バスやトラックの運転のしやすさにもつながっていますが、一方で、あのシンクロ事故を起こす危険もあります。

2時間目は改善基準告示の勉強
今回は、改善基準告示の中でも、連続運転時間のルールについて勉強します。
長時間にわたる連続運転は、疲労の蓄積、漫然運転の危険など、事故につながる要素を持っています。
初登場の社会保険労務士、坂下先生と、お馴染み飛田さんの掛け合いもお楽しみください。

旅客専用教育は『子供と高齢者の応急手当』について
旅客専用教育は、応急手当について勉強します。
今回は、子供と高齢者で発生しやすい事故について集中的に学びましょう。
誤嚥事故は、子供と高齢者で発生しやすい種類の事故です。
対策として、少なくとも、ハインリッヒ法と背部叩打法は理解しておきましょう。
✅子供の転倒事故
子供は元気がいいので、転倒した後も様子が変わらず、重大な内部障がいを見逃すことがあります。
①様子を見ておけばいいのか、②後日病院に行った方がいいのか、それとも③すぐに救急車を呼ぶべきなのか、できるだけ正しい判断ができるように勉強しましょう。
✅高齢者の失神
誰しも高齢になると、食後低血糖や下半身の筋力低下が原因となる失神の危険が出てきます。
このタイプの失神は、脳への血流が一時的に不足することが原因ですので、慌てずに少し休むことで解決します。

貨物専用教育は過積載の危険性の理解
貨物専用教育は、過積載の危険をよく理解していただきます。
いくらたくさん運んだとしても、とても割の悪い運行ですから、荷主から指示をされても、会社から指示をされても、絶対にしてはいけません。
1.事故のリスクが極端に高くなります。
2.事故を起こしたときの被害が甚大です。
3.運転士、会社、荷主、すべてが罰せられます。