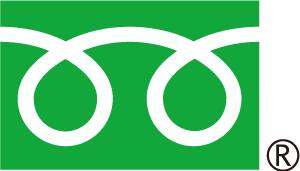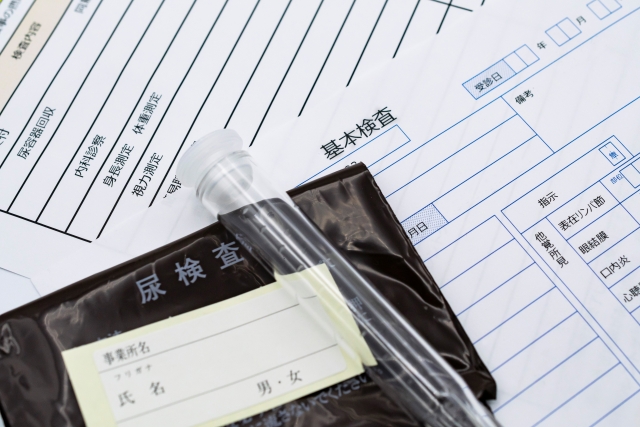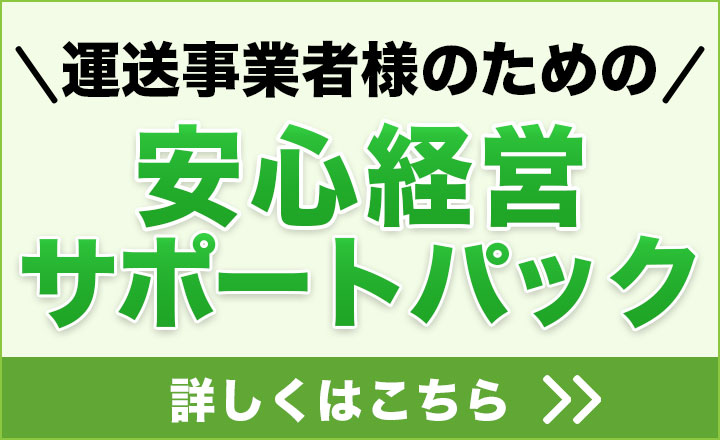健康診断は乗務員の管理の基本
健康診断は、乗務員による『健康起因による事故』を防止するための基本です。
通常は1年に1度ですが、もしも深夜労働者の条件を満たすようであれば、半年に1度の受診が義務付けられます。
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
⑩尿検査
⑪心電図検査
青文字の部分は、医師の判断によって検査を省略できる項目です。
健康診断は受けただけでは意味がない
健康診断の結果が戻ってきたら、本人は会社にそれを提出しなければなりません。
そして会社は、その結果に問題があった場合は、すぐに適切な指示をする必要があります。
その点、車と同じなので、故障個所は修理してやる必要があります。
健康診断について、監査や巡回指導で指摘を受けるとすれば、およそ以下の内容になります。
① そもそも健康診断を法令の規定どおりに受けていない。
⇒ 雇い入れ健康診断が『乗務員としての選任』よりも後・・・
⇒ 深夜労働者にあたる業務内容なのに、年1回しかやっていない。
② 健康診断はちゃんと受けているが、その後の指導がゼロ。
⇒ 再検査の指示があるのに、乗務員に全く指導していない。
⇒ 改善指示が出ているのに、改善の指導をしていない。
③ 健康診断後の指導はしているが、結論がでていない。
⇒ 再検査に行くように指示しているが、確認をしていない。
⇒ 生活習慣の改善指示はしているが、経過を聞き取りしていない。
健康診断の情報はすぐに利用できるようにする?
上記に書かれたような指導をするためには、乗務員の健康状態がすぐにわかるような工夫が必要です。
そのために、よく見かける方法としては、『乗務員台帳に健康状態の概略を記載する』などがあります。
実際には、あまりにも記入欄が小さいので、まったく機能してないのが実情です。
一番簡単な方法は、健康診断の結果をすぐに見れる状態にしておくことです。
健康診断の結果を、カギのついていない引き出しに入れておけば、誰でもすぐに確認することができて便利ですね。
「運転手の健康状態』については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第51条の規定に基づいて作成された健康診断個人票または同令第51条の4に基づく健康診断の結果の通知の写しを添付することで足りる。
なるほど、乗務員台帳と一緒に、健康診断の結果がわかる書類を保管しておけばいい、ということです。
健康診断の情報は1級品の個人情報
健康で、何一つ悪いところがなかったとしても、健康診断の結果を『他人様に覗かれる』のは気持ちの悪いものです。
ましてや、故障だらけのシニアとしては、健康診断の結果はデリケートな個人情報の最右翼に位置するものです。
それでなくとも個人情報だらけの乗務員台帳に、健康診断結果の写しが加われば、ある意味完全無敵ともいえるかもしれません。
※本当は乗務員台帳に診断結果を記載しておく必要があるのですが、『記載欄が小さくて書ききれないので写しの添付でいい』、としているわけです。
一方で、健康診断の結果情報というのは、一級品の個人情報です。
本来は、誰でもすぐに閲覧できる乗務員台帳と一緒に保管されるような種類のものではありません。
このことは行政もよく理解しているので、旧労働省では健康診断の結果について、『労働者の個人情報保護に関する行動指針』として以下のような取り扱いを求めています。
この指針は、個人情報保護法が規定される前に、今後の基本姿勢を示したものです。
第2 個人情報の処理に関する原則 3.個人情報の保管
医療上の個人情報は、原則として就業規則等においてこの指針の第2の1の(3)によることを義務づけられている者が他の個人情報とは別途に保管するものとする。
正確には『要配慮個人情報』と言います
健康診断の結果は、個人情報保護法の中で要配慮個人情報と呼ばれています。
要配慮個人情報とは、特別に配慮を要する個人情報のことで、原則として本人の同意なしに取得することは禁じられている情報のことです。
しかし、その利用目的とは別に、要配慮個人情報であることは間違いがありませんので、それなりの取り扱いをすることが必要です。
★要配慮個人情報
①人種
②信条
③社会的身分
④病歴
⑤犯罪経歴
⑥犯罪被害者としての事実
⑦身体障害、知的障害、精神(発達)障害、心身の機能の障害がある事実
⑧健康診断等の結果
※健康診断を受けたこと自体は要配慮個人情報にはあたらないので、乗務員台帳に『健康診断を受けた年月日』を記載することは問題ありません。
国土交通省と個人情報保護委員会では考え方が違う?
乗務員の個人情報については、現在の潮流に合わせて、しっかりと保護する方向で進めていただきたいと思います。
国土交通省さんは『輸送の安全が保たれる効率的な乗務員管理』を目指しているわけですから、その効用を損なわないようにした上で、乗務員の個人情報にも配慮する工夫をすればいい、ということになります。
① 乗務員台帳も施錠できる書庫に保管する。
⇒ できれば、電子データでの保管をお勧めいたします。
② 健康診断の情報はコピーを乗務員台帳とは別の場所で保管する。
⇒ 名前や性別など、本人が特定できる情報は隠した上で別の場所で保管します。
⇒ 乗務員台帳のIDを健康診断情報のコピーに記載して区別します。
⇒ こちらも、できれば電子データで保管していただきたいです。
バス会社、トラック会社ともに、健康診断結果に対する保護意識が非常に低いです。
要配慮個人情報を粗末に取り扱うと、一つ間違えば訴訟問題になりかねません。
※あと数年で、乗務員台帳の『性別欄』もなくなると思います・・・
当社はプライバシーマークのコンサルタントも行っています。
もしも個人情報の取り扱いでお困りの場合は、一度ご相談下さい。
※サポート先様のご相談のみ受け付けます。