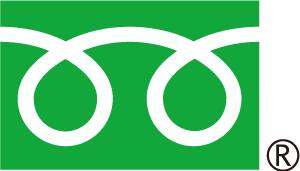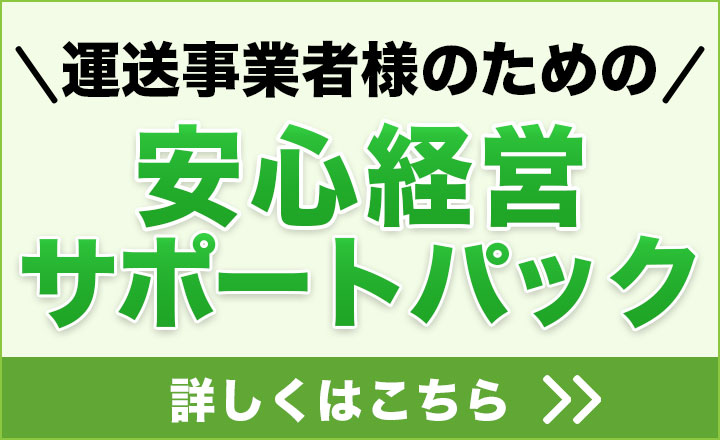工場やオフィスでは、いろいろな働き方で多くの人が活躍しています。
正社員やアルバイト、パートなどの他に、派遣や出向などの勤務形態もあります。
人員調整が比較的簡単にできる派遣、出向ですが、事業用自動車の乗務員の働き方としてはどうなのでしょうか?
工場やオフィスの働き方と比較して、注意すべき点はないのでしょうか?
派遣と出向の違いは?
派遣や出向という働き方は、通常の直接雇用型といろいろな部分で、少し違いがあります。
まずその違いについてみておきましょう。
✔派遣
『人材派遣』の許可を持った会社が、雇用している労働者を申し込みのあった事業者に派遣する形です。
派遣された労働者は、派遣先の命令指揮系統に入ります。
1日一緒に働いていても、『俺、ハケンだよ。』と言われなければ、直接雇用の労働者と区別がつきません。
籍は派遣会社に残っています。
ですから、社会保険関係もすべて派遣会社で加入します。
✔出向
(人材派遣ではない)一般の会社に在籍している労働者が、子会社や関連会社で働く形です。
籍は出向元に残す場合と、出向先に移す場合の両方があり、それぞれ在籍出向、転籍出向と呼ばれます。
この場合も派遣と同じで、命令指揮系統は出向先になります。
在籍出向の場合も、転籍出向の場合も、給料の支払いや社会保険への加入は出向元が行います。
一般的に、出向元の賃金体系と出向先の賃金体系に違いがある場合は、その差額を負担するのは出向元になります。
『人材派遣』の許可を持った会社が、雇用している労働者を申し込みのあった事業者に派遣する形です。
派遣された労働者は、派遣先の命令指揮系統に入ります。
1日一緒に働いていても、『俺、ハケンだよ。』と言われなければ、直接雇用の労働者と区別がつきません。
籍は派遣会社に残っています。
ですから、社会保険関係もすべて派遣会社で加入します。
✔出向
(人材派遣ではない)一般の会社に在籍している労働者が、子会社や関連会社で働く形です。
籍は出向元に残す場合と、出向先に移す場合の両方があり、それぞれ在籍出向、転籍出向と呼ばれます。
この場合も派遣と同じで、命令指揮系統は出向先になります。
在籍出向の場合も、転籍出向の場合も、給料の支払いや社会保険への加入は出向元が行います。
一般的に、出向元の賃金体系と出向先の賃金体系に違いがある場合は、その差額を負担するのは出向元になります。
派遣や出向の労働者を乗務員として選任していいの?
結論からもうしあげますと、まったく問題ありません。
但し、少しだけ条件があります。
事業用自動車の乗務員に選任してはいけない労働形態を覚えていますか?
旅客自動車運送事業運輸規則
第三十六条
旅客自動車運送事業者(中略)は、次の各号の一に該当する者を前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。
一 日日雇い入れられる者
二 二月以内の期間を定めて使用される者
三 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
四 十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者
旅客自動車運送事業運輸規則
第三十六条
旅客自動車運送事業者(中略)は、次の各号の一に該当する者を前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。
一 日日雇い入れられる者
二 二月以内の期間を定めて使用される者
三 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
四 十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者
基本として、上記の4つの条件に当てはまらなければ雇用形態に関わらず乗務員として選任することができます。
後は、個々の細かいルールに従うだけです。
派遣や出向の乗務員さんの選任手順を復習しましょう
新しい職場で、新たに乗務員として選任されるためには、一定の儀式を経なければなりません。
健康診断であったり、初任診断であったり、教育であったり・・・
①健康診断
派遣元や出向元の会社で直近に受けた(1年以内)健康診断書の写しを保管しておきます。
※法令上の問題ではないのですが、事業用自動車の乗務員という職責を考えると、個人的には雇い入れ時の健康診断は行ったほうがいいと思います。
②運転記録証明書の取得
事故惹起者でないかどうかの確認をします。
③初任診断
適性診断を受ける必要があります。
②で事故惹起者であることが分かった場合は、特別診断ⅠないしはⅡを受けることになります。
また、派遣、出向された方が65歳以上の場合は、適齢診断を受ければOKです。
④初任運転者教育
※一般貸切の場合
座学10時間以上、実地訓練20時間以上が必要です。
※それ以外の旅客自動車の場合
座学6時間以上、実地訓練は実施することが望ましい、とされています。
一般貸切以外の乗務員の場合、選任される日前3年間に他の旅客自動車運送事業者において乗務経験がある場合は、③と④が免除される場合があります。
派遣元や出向元の会社で直近に受けた(1年以内)健康診断書の写しを保管しておきます。
※法令上の問題ではないのですが、事業用自動車の乗務員という職責を考えると、個人的には雇い入れ時の健康診断は行ったほうがいいと思います。
②運転記録証明書の取得
事故惹起者でないかどうかの確認をします。
③初任診断
適性診断を受ける必要があります。
②で事故惹起者であることが分かった場合は、特別診断ⅠないしはⅡを受けることになります。
また、派遣、出向された方が65歳以上の場合は、適齢診断を受ければOKです。
④初任運転者教育
※一般貸切の場合
座学10時間以上、実地訓練20時間以上が必要です。
※それ以外の旅客自動車の場合
座学6時間以上、実地訓練は実施することが望ましい、とされています。
一般貸切以外の乗務員の場合、選任される日前3年間に他の旅客自動車運送事業者において乗務経験がある場合は、③と④が免除される場合があります。
一般貸切の場合は、例外なく、上記のプロセスを実施する必要があります。
出向元と出向先の両方で選任できる?
上でお話ししたように、一般貸切の場合は、選任されるたびにそこそこ大変な選任プロセスをたどらなければなりません。
出向先での仕事が終わって出向元に戻った場合、出向元で選任するにはまた上記の選任プロセスを繰りかえさなければならず、これはかなり大変な労力です。
ここから先を
お読みになるには
ログインが必要です。
お読みになるには
ログインが必要です。
サポート契約を結んでいただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。
- 毎月最新の乗務員教育教材が届きます(Eラーニング対応)
- AIでは検索できない重要情報満載の記事が読み放題です
- 電話・メールで業務の相談し放題です
- その他、特典が満載です