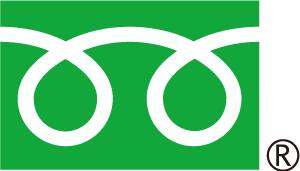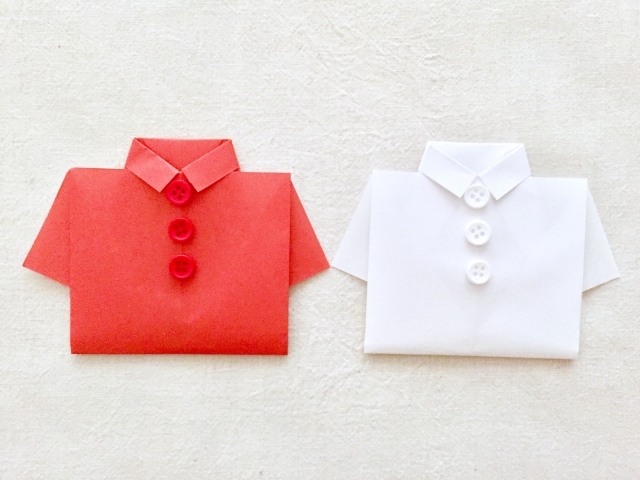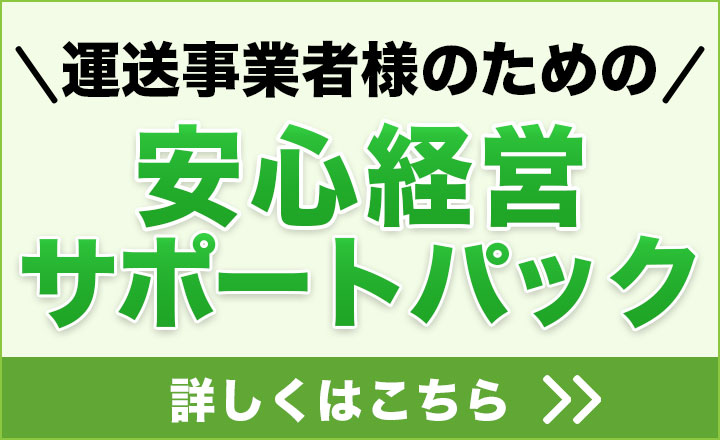先日、ある事業者さんが作成された乗務員台帳をチェックしていて、乗務員の選任手順に問題を見つけました。
適性診断の受け方に問題があったのですが、間違いの原因は「乗務員の選任」という儀式を理屈で理解していないという現実が根底にあるようです。
そこで、今回は「乗務員の選任」という儀式の意味について考えてみたいと思います。
乗務員の選任には手順がある
事業用自動車(緑ナンバー)に運転手さんを乗務させるためには一定の手続きが必要です。
緑ナンバーと一言で言っても、いろいろな種類の車両がありますし、それぞれに基準はあるのですが、今回はその中でも一番厳しい『貸切バス乗務員の選任』についてお話しします。
ANAやJALなどの航空会社、JRなどの鉄道会社で考えてください。
これらの会社で、パイロットや運転手としていきなり雇用されることがありますか?
まず従業員として雇用されて、一定の訓練及び選考を経てパイロットや運転手に選任されるわけです。
事業用自動車の乗務員も基本的には同じ考え方で進めなければなりません。
【免許がある=資格がある】ではありません。
まずは健康診断
新しく雇い入れた乗務員(候補)が健康であるかどうかは、雇用する側のとても重要な関心事です。
二種ドライバーが慢性的に不足している昨今、本人の「私は健康です。」という申告を信じたい気持ちはわかりますが、旅客乗務員の責任の重さを考えれば、やはり客観的な証明を取っておきたいところです。
※但し、その場合は入社以前3ヶ月以内に受診したものだけが再利用できます。
忘れがちな運転記録証明書
新たに選任予定の乗務員について、運転経歴書などでこれまでの事故や違反の履歴を知っておくことも必要です。
基本的には本人の申請が必要ですが、代理権を証明する書類(委任状など)があれば、会社が代理で申請することも可能です。
自動車安全運転センター
違反や事故がなければ問題ないのですが、運転記録証明書によって『事故惹起運転者』であることが判明した場合。
その場合は、この後に説明する『適性診断』に違いがでてきます。
①死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者
②死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者
適性診断を受ける
運転記録証明書によって事故惹起者ではないとわかっても、適性診断は受けされなければなりません。
この場合の適正診断は『初任診断』と呼ばれています。
しかし、選任される乗務員さんが65歳以上であった場合には、『適齢診断』を受診することで「初任診断」を受診したことになります。
NASVA初任診断
初任運転者が『事故惹起者』であった場合には『特定診断』を受ける必要があります。
この場合も初任教育の一環として受診した場合は、『適齢診断』と同様に『初任診断』の代わりと考えることが可能です。
初任乗務員教育(座学・実地)
雇用した従業員を乗務員に選任するには社内での教育が必要です。
特に貸切バスの場合は実務教育(路上)の時間が長いので注意が必要です。
初任運転者の教育については、以下の記事をご覧ください。
これらの社内教育は、適性診断の結果を受けて個別に実施されるものでなくてはいけません。
お読みになるには
ログインが必要です。
- 毎月最新の乗務員教育教材が届きます(Eラーニング対応)
- AIでは検索できない重要情報満載の記事が読み放題です
- 電話・メールで業務の相談し放題です
- その他、特典が満載です