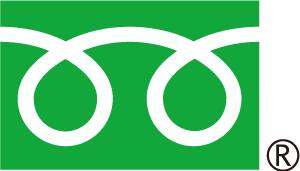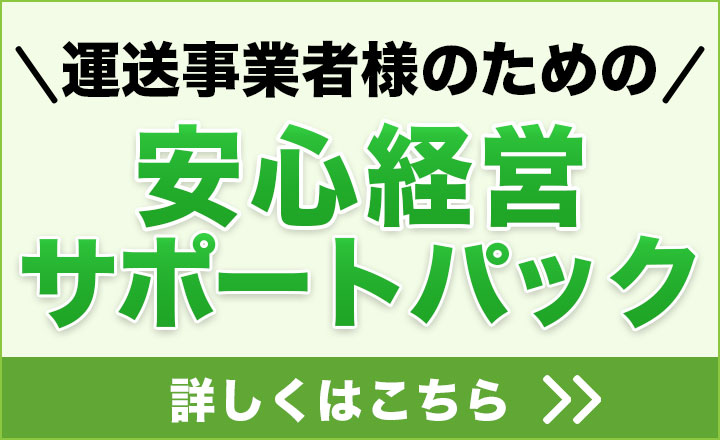貨物運送事業や旅客運送事業において、市街化調整区域にトレーラハウスの事務所を設置して事業を開始する方法があります。
昨年くらいからお問い合わせが多く、当社の許可実績も増えてきましたので、一度基本を解説しておきたいと思います。
市街化調整区域とは?
日本全国の土地には市街化を積極的に進める場所と、できるだけそのままの状態を保持しておきたい場所があります。
このような線引きをしておかないと、無秩序に市街化が進められて環境の破壊が著しくなります。
都市計画的にも、限られた予算の中で効率的なインフラ整備をするためには、範囲が限定されていた方が有利です。
登記簿謄本に書かれている、『宅地』や『田』などとは別の法律によって決められています。
また、『第一種低層住居専用地域』や『工業地域』などの用途指定とも意味が違います。
調整区域には建物が立たない?
基本的には自治体の建築許可が下りないので、特定のもの以外は建築物が立ちません。
では、何も建たないのかというと、そういうこともありません。
地域の生活に必要な、ガソリンスタンドやコンビニ、大手運送会社の物流拠点、自動車修理工場などは許可になる場合があります。
せっかく市街化せずに今現在の環境を保持しようと決めた地域に建物が建ってしまうと、都市計画の意味がなくなってしまいます。
市街化調整区域に無許可で建築物を作ると、違法建築物となって、撤去を命じられることもあります。
※市街化調整区域は基本的に田舎です。そんなところで、いきなり無許可建築を始めれば、すぐに通報されます。
車庫は広い方がいい
貨物自動車運送事業を始めようとする場合、最低でも5台のトラックを用意する必要があります。
旅客運送事業の場合も、大型バスを使用するのであれば、最低5台のバスを用意しなければなりません。
トラックやバスの車庫のために、広い土地を探すとどうしても市街化調整区域の土地を検討しなければならなくなります。
市街化地域でも探せますが、周辺環境に問題があったり、維持するためのコストが倍増したりします。
しかし、実際の運用を考えると同じ賃料であるならば、車庫は広ければ広い方がいいと考えるのが普通です。
市街化調整区域が車庫の候補地として人気がある理由がここにあります。
市街化区域で、営業所の建物に併設した車庫を探すのはいろいろな意味で大変です。
特に前面道路との関係は重要で、市街化区域の厳しい道路事情では車庫内での転回なども含めて、より広い車庫が必要という矛盾が生じます。
建築物でなければいい?
本当なら営業所に車庫が併設されているのが理想ですが、それが不可能な場合、事業用自動車の車庫は、拠点となる営業所から一定の距離に設置しなければなりません。
トラックなら地域差はありますが、5キロから10キロ。
バスは全国2キロとなっています。
市街化区域の土地を車庫として利用する場合、建築許可をとって営業所を車庫敷地内に建設してしまえばいいのですが、市街化調整区域ではそれもできません。
トレーラーハウスは車輪がついており、けん引されるためのフックもついています。
つまり、いつでも必要に応じて移動することができるので、建築物にはあたらないと考えられるわけです。
これなら、市街化調整区域にも設置できますし、それを営業所として利用して許可申請することも可能です。
トレーラーハウスを自分で買ってきた・・・
市街化調整区域にトラックの車庫として1500㎡の土地を借りました。
友人が所有しているトレーラーハウスを安く購入して、自分で設置しました。
ここを本社営業所として一般貨物運送事業の許可を申請したいと考えています。
大丈夫でしょうか?
こちらがいくら主張しても、自治体が認めなければ建築物のあつかいになる可能性があります。
自分でトレーラハウスを購入して、土地に設置してから私たち行政書士に許可申請の依頼をされても、100%許可になるとは言えません。
行政への確認が大切
『トレーラーハウスが建築物ではない』と認められるためには一定の条件と、それを行政に確認する手順が必要です。
それを守らずに申請しても、不許可になる可能性があります。
日本トレーラハウス協会
手数料が必要ですが、各自治体への設置確認をしてくれます。
一番簡単な方法は、購入するトレーラーハウスのメーカーやバイヤーを通じて、日本トレーラハウス協会へ依頼することです。
また、当社に最初からご相談いただければ、設置確認も含めてお引き受けいたします。
許可条件を満たしたトレーラーハウスを制作するメーカーのご紹介もしておりますので、お気軽にご相談ください。
非建築物には条件が必要
トレーラーハウスが非建築物として認められるためには、いろいろな条件が必要です。
代表的なものが、ナンバーの有無でしょうか。
一昔前までは、ナンバープレートの付いていない車両でも認められましたが、今では多くの自治体でナンバー付き車両でなければいけないとされています。
好みのトレーラーハウスを購入した後で、許可にならないのでは元も子もないので、トレーラーハウスでの事業をお考えの皆さんは事前にご相談ください。
最初からご相談ください
車庫として使用を考えている土地に、すでに違法建築物がある場合は注意が必要です。
※違法建築物には、コンテナハウスのポン置きも含めます。
すでに違法な状態にある土地から自治体に照会をかけても、まず認められることはないからです。
これから事業用自動車の車庫を探そうとお考えの皆さま。
市街化調整区域にトレーラーハウスで営業所を設置しようとお考えの社長さん。
いろいろとご自身で動かれる前に、ぜひ当社にご連絡ください。
土地選びからトレーラーハウスの購入、設置確認から許可まで、すべてサポートいたします。