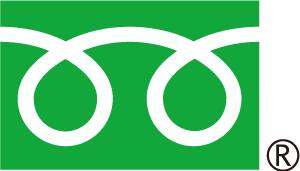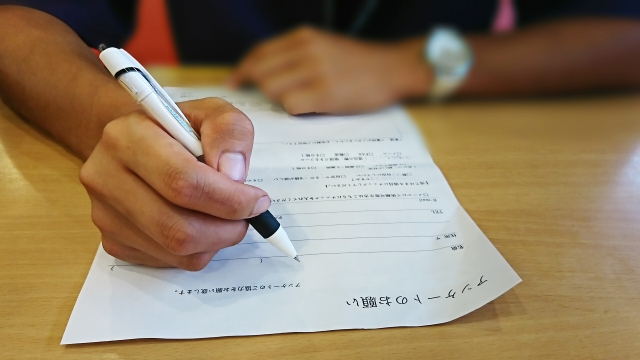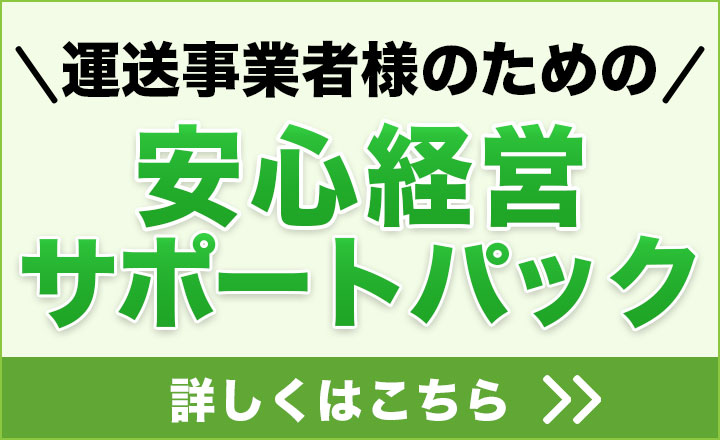適齢診断はなんのため?
事業用自動車のドライバーには、適性診断の受診が義務付けられている場合があります。
一つは、初めて事業用自動車に乗務する場合に受ける初任診断。
そして、もう一つが今回の話題である適齢診断です。
貨物においても旅客においても、65歳を過ぎると適齢診断の受診義務が発生します。
① 65歳になったら、66歳の誕生日を迎えるまでに1回目を受ける。
※65歳以上で初任運転者になる場合は、初任診断の代わりに適齢
② それ以降は75歳になるまで3年に一度受診する。
③ 75歳になったら、そこからは毎年受診する。
① 65歳になったら、66歳の誕生日を迎えるまでに1回目を受ける。
※65歳以上で初任運転者になる場合は、初任診断の代わりに適齢
② それ以降は75歳になるまで3年に一度受診する。
③ 75歳になったら、そこからは毎年受診する。
適性診断は受けただけでは意味がない
適性診断はただ受診しただけでは意味がありません。
実際、安全のために必要なのはその後に行われる特別教育の方です。
学生さんなら高校受験や大学受験、社会人であれば資格試験などで模擬試験を受けることがあると思います。
よく模擬試験の結果に一喜一憂している人を見かけますが、模擬試験の結果をそういう風にとらえている人は、まず合格しません。
私も資格チャレンジのときは多くの模擬試験を受けましたが、悪い成績の時の方が得をしたと思っていました。
なぜなら、試験は『自分の弱点を炙り出すためにある』のであって、良い点数は本番でとれればいいからです。
よく模擬試験の結果に一喜一憂している人を見かけますが、模擬試験の結果をそういう風にとらえている人は、まず合格しません。
私も資格チャレンジのときは多くの模擬試験を受けましたが、悪い成績の時の方が得をしたと思っていました。
なぜなら、試験は『自分の弱点を炙り出すためにある』のであって、良い点数は本番でとれればいいからです。
弱点が見つかったらラッキー!
適齢診断によって、自分の弱点が明らかになります。
この弱点のほとんどは加齢によるもので、対策次第では改善できる可能性のあるものです。
適齢診断では、受けたテストについて、①診断項目 ②診断結果が示されています
★診断後の特別教育でやるべきこと
① 診断の内容に応じて、問題点の改善になるような教育をする。
※その項目に問題がなければちゃんと褒めることも大事
② 教育を受けた本人の感想を記録する。
③ 使用した教材を記録する。
★診断後の特別教育でやるべきこと
① 診断の内容に応じて、問題点の改善になるような教育をする。
※その項目に問題がなければちゃんと褒めることも大事
② 教育を受けた本人の感想を記録する。
③ 使用した教材を記録する。
適齢診断を受けた人を講師に教育する
適齢診断の一部項目について、とてもいいスコアを出した高齢ドライバーがいたとします。
私の顧問先のバス会社では、このようなドライバーを適齢診断後の特別教育の講師にしているところがあります。
この方法は、素晴らしくリーズナブルな良い方法です。
この場合のリーズナブルは『コストが低い』という意味ではなく、『費用対効果が高い』と考えてください。
この場合のリーズナブルは『コストが低い』という意味ではなく、『費用対効果が高い』と考えてください。
特別教育は改善のための第一歩
業務を継続的に改善していく方法の一つに、マネジメントシステムがあります。
マネジメントシステムにおける診断は『D(行動)』です。
業務を継続的に改善していくためには、PDCAサイクルを回していくことが大切です。
適齢診断を受けることがDだとしたら、その後の結果がC、そして特別教育がAになるでしょう。
マネジメントシステムにおいて、特に大切なのはCとAです。
CとAが欠けたマネジメントシステムは、失敗の繰り返しであり、いつまで経っても改善には届きません。
特に、Aがなければ模擬試験の結果に一喜一憂している受験生と同じで、改善(合格)からはどんどん遠くなってしまいます。
適齢診断も、診断後の特別教育(A)があってこそ、継続的な改善につながるのです。
適齢診断を受けることがDだとしたら、その後の結果がC、そして特別教育がAになるでしょう。
マネジメントシステムにおいて、特に大切なのはCとAです。
CとAが欠けたマネジメントシステムは、失敗の繰り返しであり、いつまで経っても改善には届きません。
特に、Aがなければ模擬試験の結果に一喜一憂している受験生と同じで、改善(合格)からはどんどん遠くなってしまいます。
適齢診断も、診断後の特別教育(A)があってこそ、継続的な改善につながるのです。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】