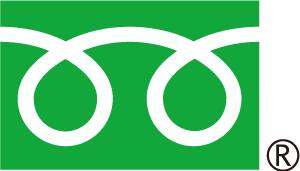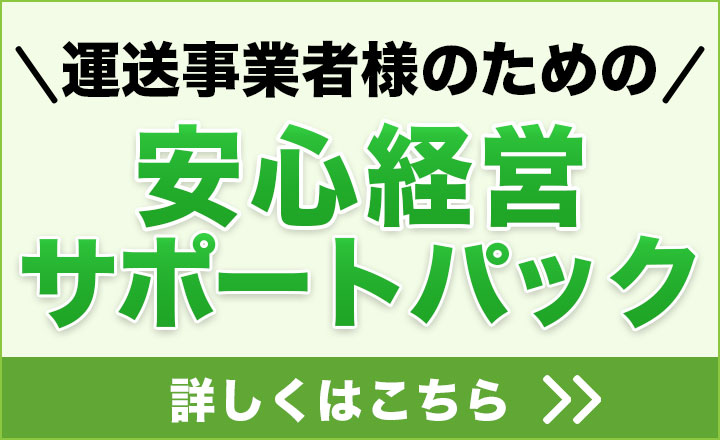適齢診断は65歳から(貨物・旅客共通)
適齢診断は、加齢による運転能力の衰えがないか、客観的に分析するために受診します。
- 65歳から3年ごと
-
65歳の誕生日を迎えた段階で、事業用自動車のドライバーとして選任されているのであれば、当人が65歳である間に適齢診断を受診します。
仮に、65歳で最初に受診した場合、次に受診するのは3年後の68歳です。
そのままドライバーとして選任されているとするなら、次は71歳、さらに74歳で受診することになります。
75歳からは毎年受ける(旅客のみ)
ドライバーとして選任されて75歳を迎えたら、そこからは毎年適齢診断を受診することが必要になります。
- 微妙なケース
-
仮に、70歳でドライバーに選任されて、その後73歳で適齢診断を受けた場合を考えてみましょう。
その次は、3年後の76歳でもよさそうなものですが、75歳になると強制的に診断を受ける義務が生じます。
そこから毎年受診するのは同じです。
適齢診断は年度で考えない、年単位で考える
最初、65歳と4カ月で適齢診断を受診したドライバーさんがいたとしましょう。
この方、次は68歳の間に受診すればいいのでしょうか?
- 適齢診断は健康診断と同じ仲間
-
上記の例では、68歳4カ月(正確には、前回の受診日の当日)までに受診する必要があります。
この辺の考え方は、健康診断と同じ。
月単位ではなく、日単位で管理する必要があります。
では、75歳以上の場合は?
やはり同じです。
75歳3カ月で受診したとすると、翌年の同日(同日OK)までに受診する必要がでてきます。
- 指導及び監督の指針
-
適齢診断を65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後75才に達するまでは3年以内ごとに1回受診させ、75才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後1年以内ごとに1回受診させる。
※『年度ごと』ではなく、『年ごと』と書かれているのがミソです。
慌てて受けない方がいい?
65歳になってすぐに適齢を受けてしまうと、68歳になったとき、またすぐに受診しなくてはいけなくなってしまいます。
つまり、できるなら、少し余裕を持たすためにも、65歳10カ月とか、66歳直前とか、そういう工夫をした方が、あまり慌てなくて済むと思います。
65歳3カ月のドライバーを雇用したら?
ここから先を
お読みになるには
ログインが必要です。
お読みになるには
ログインが必要です。
サポート契約を結んでいただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。
- 毎月最新の乗務員教育教材が届きます(Eラーニング対応)
- AIでは検索できない重要情報満載の記事が読み放題です
- 電話・メールで業務の相談し放題です
- その他、特典が満載です