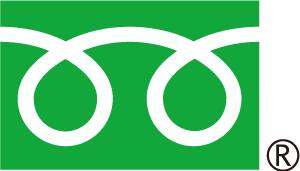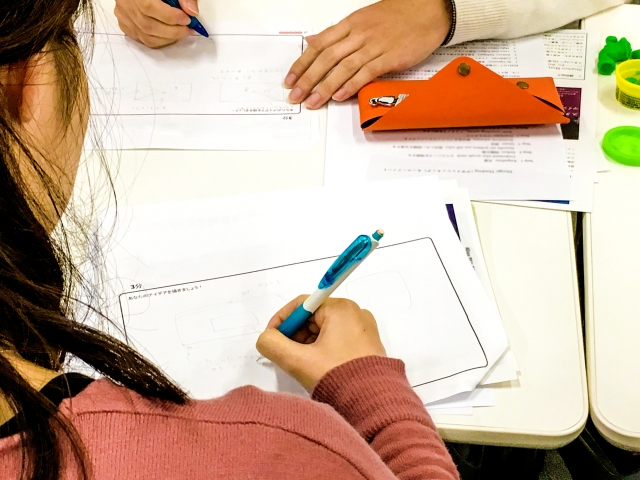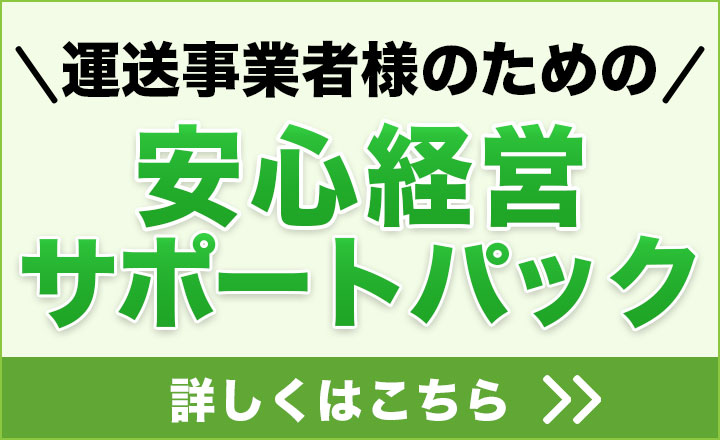今回は貸切バス事業の監査、巡回に対応するための注意事項について少しアドバイスを。
監査は特に怖いですから、日ごろからしっかりと準備しておくことが大事です。
監査・巡回で指摘されやすいポイント
監査は突然やってきます。
ですから、普段からちゃんとやっているつもりの事業者さんでも、ノーミスでクリアすることはむずかしくなります。
運行管理者いないとか、整備管理者の実態がないなど、本当に初歩的な違反は論外ですが、日ごろキチンとやっている事業者さんでもおろそかになりやすいポイントがあります。
①営業区域外違反
悪意なく気づかずにやってしまっているパターンが多いです。(60日車)
②健康診断関係の違反
1年に一回なのですが、ついつい忘れてしまいがちです。(警告~80日車)
③適性(適齢)診断の受診義務違反
これも、ついつい後回しなったケースが多いですね。(警告~60日車)
④運転手の教育関連義務違反
教育は大変重要視されています。これをいい加減にやると痛手になります。(警告~60日車)
安全性評価認定(セイフティ)を取っても監査は来ます。
ヒトツボシ★だろうが、ミツボシ★★★だろうが、監査には何の関係もありません。
監査は容赦なく来ます。
そして、しっかり指導されます。
ちなみに・・・
埼玉県でも★★★の会社さんが20日車のペナルティを受けた例があります。
自己点呼に注意!!
自己点呼ってわかりますか?
乗務員が運行管理者を兼ねている場合に多い違反です。
今は最低二人選任しなくてはいけなくなりましたから、あまりこの違反はないでしょうが・・・
それでも、二人のうち一人が乗務員を兼ねている場合は起きる可能性がある違反行為です。
統括運行管理者がインフルエンザで倒れたとします。
基礎講習を受けた補助者が選任されていればいいのですが、それもない場合。
運行管理者でもある乗務員の体調管理、アルコールチェックは誰がやるのでしょう?
自分で自分をチェックしてはいけないことは・・・わかりますよね。
監査をやみくもに恐れる必要はありませんが、日ごろからいつ監査に入られてもいいように準備(?)しておくことが大事です。
この心構えが結果として安全運行につながり、最終的には安定経営につながると考えましょう。
地方の会社は監査端緒に注意
業務の分業化のためや、事業承継のために会社を分社化したり、主たる営業所を地方から東京に移転させたタイミングで監査が入ることがあります。
このような何かのきっかけで監査が入ることを監査端緒(かんさたんしょ)といいます。
日ごろからキチンとした体制をとっている場合はいいのですが、そうでない場合は厳しい結果が出ることもあります。
群馬県に本社と営業所のある会社が、本社と営業所の両方を東京に移そうとした事例で監査が入ったことがあります。
この場合、群馬に本社と営業所が残っていれば、監査にはならなかったかも?しれません。
地方は監査もきびしい?
そんな印象があります。
偏見かもしれませんし、事実なのかもしれません。
東京よりも地方が厳しいと思うのは私だけでしょうか・・・
気のせいならいいのですが。
覆面監査が話題になったことも・・・
現在、貸切バスの監査については、
①一般監査
②特別監査
③街頭監査
の3種類が用意?されています。
1の特別監査は>最近大きな事故を起こしたような、要注意(失礼ですね。ごめんなさい。)事業者に対して行われるものです。
2の一般監査は監査端緒と呼ばれる、何がしかの疑いがもたれるような事業者に対して先行して行われる監査です。
よくある例では、運輸局以外のお役所(労働関係の機関、道路管理者など)からのチクりがあった場合です。
労働者が10人もいるのに、一人も労災に加入していない・・・など
3の街頭監査は行政書士の私より事業者の皆さんの方がよくご存じですね。
駅や空港などでいきなりトントンされる、あれです。
そこに今回、覆面監査なるものが追加されるようです。
民間機関の一般人が乗り込むようです。
各支局の監査担当者では面が割れています。
ですから、民間機関(バス協?)の一般職員さんがツアー客にまぎれてバスに乗り込んでくるようです。
かなり念の入った話です。
一般のお客様のフリをしてバスに乗り込んだ調査員は、おおむね以下の内容を調査するようです。
①乗務員の休憩時間の確保
②シートベルトの着用状況(お客さまへの装着のお願いも含め)
③交代運転者の配置状況
④危険運転の有無、車内、車外の表示
具体的には?
調査員が収集するデータは、すべて映像や写真、音声で記録をすると考えられます。
明らかな交代運転手の配置義務違反や危険運転、連続運転違反などは監査端緒となるでしょうから、すぐに一般監査が待っていることになります。
しかし、その場で明確な違反が見つからなかったとしても、記録の改ざんが疑われるようなツアーだった場合には、やはり一般監査が入って、調査員の記録と営業所に残る各記録類が突合されて、そこに改ざんがあればペナルティを受けることになります。
??改ざんが疑われる?それはどんな場合?
やはり危ないのは交代運転者の配置違反
現在はデジタルにせよアナログにせよ、タコグラフが正確にデータを刻んでいますから、そうそう記録を改ざんすることはできません。
できるとすれば、実際には基準に定められた形で休息をとっていないのに、休息扱いにして拘束時間をいじったり、1運行を2運行に広げてしまっている違反。
これは実際に調査員が拾い集めた情報と、営業所に残る書類の突合でしかわかりませんから、この覆面調査の狙いはこのあたりにある、とも考えられます。
交代運転者が配置されていても注意が必要
運転手の交代のタイミングで必ず行わなければならない儀式がありますね。
ここも調査員は見ている(撮影している)可能性がありますね。
交代運転手が交代時に必要部分の点検をやっているか?なんて、私が調査員なら狙いたいポイントです。
監査サギには十分注意
「オタクの監査予定の情報が入った。危ないよ!オタク!」
私が主に仕事をさせていただいている、東京、埼玉のお客様からのご相談ですが、こんな詐欺まがいの電話がかかっているようです。
「えっ?本当ですか?私はどうすればいいんですか?」
「監査対策に〇〇万円支払ってくれれば、監査で違反にならないようにアドバイスするよ。」
このような電話をかけているのは、残念ながら私と同じ行政書士です。
手法としては、とにかく事業者の不安を煽って、少しでもお金にしようという、極めて古典的な詐欺です。
①監査の情報は洩れません
情報ですから、絶対にもれない、とは言えませんが、行政書士がひょいひょい手に入れられるような種類のものではありません。
②監査は突然やってきます
お読みになるには
ログインが必要です。
- 毎月最新の乗務員教育教材が届きます(Eラーニング対応)
- AIでは検索できない重要情報満載の記事が読み放題です
- 電話・メールで業務の相談し放題です
- その他、特典が満載です