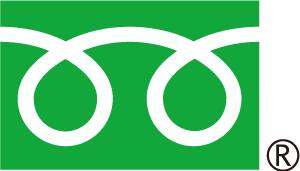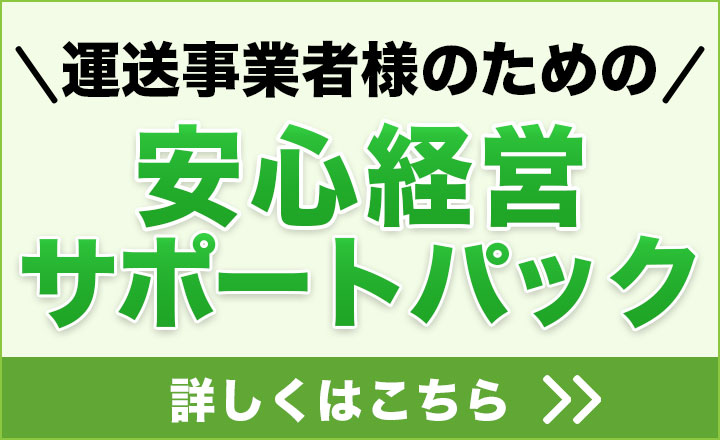ご遺体は貨物扱いになる
ご遺体は、法律上、物の扱いになります。
よって、ご遺体を車で搬送するには、貨物自動車運送事業の許可を取得することが必要になります。
霊柩運送事業は、この法律の名称のとおり、貨物自動車(トラック)運送事業の仲間とされています。これは民法上の規定によって「人間」はその死を境に「物」に変わるため、その「物」であるご遺体を搬送する霊柩運送事業は、貨物自動車運送事業であるということが理由となっています。
(一般社団法人全国霊柩自動車協会さんのホームページより)
(一般社団法人全国霊柩自動車協会さんのホームページより)
施設の要件は一般貨物とほとんど変わらない
霊柩車の申請と言っても、一般貨物の新規申請には違いがありませんから、営業所や休憩仮眠施設、車庫など、必要な施設に大きな違いはありません。
車両の台数と管理者の部分が少し甘い
一般貨物の場合、最低車両数は5台~となっていますが、霊柩車の場合は1台~OKです。
✅運行管理者
運行管理者の選任は必要ですが、営業所の総車両数が5台未満であれば、資格者である必要はありません。
✅整備管理者
整備管理者についても同じです。
総車両数が5台未満であれば、資格者である必要はありません。
法令試験や資金要件などは同じ
法人であれば役員が、個人であれば本人が、役員法令試験を受験して合格する必要がある点についても同じです。
資金要件についても、基本が変わることはありません。
許可後の運行管理に違いはあるの?
ちょっとした違いがあるとすると、運行管理者と整備管理者について、営業所単位での選任は必要なのですが、支局保安課への選任届の提出は不要となっています。
但し、運行管理については、一般貨物と何ら変わるところがありません。
日々、日常点検は必要ですし、整備管理者による運行の可否判断、運行管理者による点呼など、全く同じレベルの運行管理が求められます。
霊柩車だからと言って、甘く考えてはいけません。
令和7年4月から霊柩事業者にも巡回指導?
中部地方のサポート先からの情報です。
ここから先を
お読みになるには
ログインが必要です。
お読みになるには
ログインが必要です。
サポート契約を結んでいただくと、会員限定サービスをご利用いただけます。
- 毎月最新の乗務員教育教材が届きます(Eラーニング対応)
- AIでは検索できない重要情報満載の記事が読み放題です
- 電話・メールで業務の相談し放題です
- その他、特典が満載です