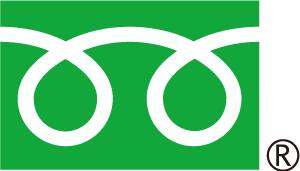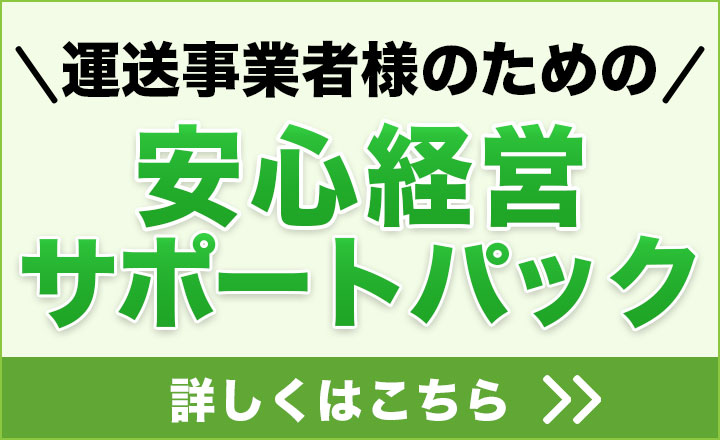貨物運送事業の許可更新制度は今どこに?
現在、自民党のトラック輸送振興議員連盟が中心となって、貨物自動車運送事業法の改正案の取りまとめが行われています。
1.事業許可の更新制度導入
更新制度導入を望む理由として、以下のようなものがあげられています。
①一定の期間(たぶん5年)ごとの更新によって、違反常習の悪徳事業者を業界から締め出すことができる。
②経営基盤や安全対策が脆弱な事業者を排除することができる。
①+②の効果によって、経営基盤の確かな(適切な人件費を確保できる・安全にお金がかけられる)事業者が残るだろうと期待しているわけです。
2.下限運賃の導入
「標準的な運賃」の試みがあまり効果を上げなかったことで、運賃の下限制限を導入したい、という動きが強くなっています。
車種によって最低限のコストを計算し、そのコストに適正利益を加算した運賃を下限とする案が有力のようです。
モデルとなっているのは一般貸切の制度
一般貸切旅客自動車運送事業では、2016年に道路運送法が改正され、翌2017年の4月から正式に更新制度がスタートしました。
更新制度の導入によって、貸切バスの業界はどのような変化したのでしょうか?
▶極端に財務内容が悪かったり、安全意識の低い事業者は淘汰されるようになった
⇒これは間違いありません。
更新を依頼されてきたものの、到底更新審査に耐えられる経営内容ではなく、廃業や吸収される事業者さんも少なくありません。
▶貸切バス事業者安全性評価認定制度が定着した
⇒更新のためには、経営者が受ける法令試験に合格する必要があります。
貸切バス事業者安全性評価認定制度で★を取得していれば、この試験が免除されることから、認定を受ける事業者が増えました。
▶財務諸表に意識を向ける経営者が増えた
⇒財務状況の悪い会社(直近年度で債務超過・直近3期連続で経常赤字)は更新ができないことから、自社の財務内容を財務諸表で確認できる経営者が増えました。
▶行政処分に敏感になった
⇒更新から更新までの間で、毎年行政処分を受けた会社は、有無を言わさず更新不可となります。
このことから、以前よりも巡回指導や行政処分に敏感な事業者が増えたと感じます。
⇒この場合の「行政処分を受ける」という意味は、る輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分のことを指します。
一般貸切の場合、50日車以下の処分では、実際に車両が止められることはありません。
その理由は、こんなところにあるのです。